竹富島の島人とゆんたく(おしゃべり)
安里屋の美女クヤマは1722年に生まれ、1799年、78歳でこの世を去りました。
竹富島にはクヤマの誕生の地が残り、現在七代目に当たる方がトートーメー(位牌)を守っているそうです。
当時、なぜクヤマが役人の目差主の申し出を断ることができたのか、「安里屋ユンタ」の歌を誰が作ったのかということはいまでも謎に包まれていますが、生涯独身を貫いたクヤマはたいへんな才色兼備であったそうです。
役人から畑を譲り受けたクヤマは数人の人夫を雇い、畑の真ん中に酒甕を置き、最初に酒甕にたどり着いた者がお酒を飲めるという条件をつくり、畑の四方八方から人夫を酒甕に向けて競わせながら畑仕事をさせたという逸話もあるそうです。

島の人に「安里屋ユンタ」を二十三番まで歌うことはないのですか、と尋ねたところ、
「通常は5~6番くらいまでですね。歌劇にしたものを老人クラブが踊るときには17番まで歌っていますけど」
と教えていただきました。運良く歌劇に出逢えると楽しいでしょうね。
また、竹富島に駐屯していた高知、愛媛、沖縄、新潟出身の日本兵「大石隊」は島民と仲良くなり、「安里屋ユンタ」の囃子「ハーリヌ チンダラカヌシャマヨ」が「我も死んだら神様よ」と聞こえたらしく、勇気づけられたという話もありました。
印象に残るのは、ひとつの目的にみんなが一丸となる“うつぐみ(打組)”の精神、そして「人頭税のような過酷な悪税を乗り越えられたのは竹富のひとの気質だと思います。
「竹富島の道には側溝やドブはないでしょう?
これは珊瑚礁の島だから雨が降っても サーっと雨が地面に吸い込まれてなくなるからです。
島のひとの気質もこうしたさっぱりとした気質だからウジウジと暗くならずに耐えられたのだと思います」
と島の土地と島人の気質を語るおばぁの底抜けの笑顔でした。

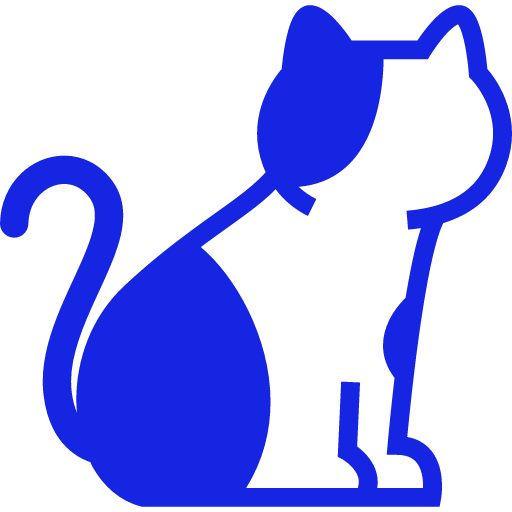 島風の記憶と希望
島風の記憶と希望 
