竹富島に伝わる古謡「安里屋ユンタ」
古謡「安里屋ユンタ」は次のような歌い出しではじまります。
「ヒヤ 安里屋ぬクヤマによ サーユイユイ」

クヤマは竹富島で生まれ、暮らしていた実在の女性です。
琉球王府が過酷な人頭税を課していた時代、人頭税の地割のために竹富島にやってきた役人・目差主が16歳の美しいクヤマを賄女(いわゆる現地妻)に望むも、いずれ島を去る役人は嫌だとあえなくクヤマに肘鉄砲を食わされます。
クヤマに振られた目差主は腹いせにクヤマ以上の美女を探し求めていたところ、仲筋の兼真家の美女イスケマと出逢います。
目差主がイスケマを所望したところ兼真家は大喜びで承諾し、目差主も大喜びでイスケマを迎えます。
ンブフル(竹富島内にある地名)の石畳道から地面さえ踏まさないようにイスケマを大事に官舎へ連れて帰り、八つ折りの屏風の内側で腕を枕に…という内容が延々23番まで続いています。
「安里屋ユンタ」(竹富島)
一、ヒヤ 安里屋ぬ クヤマによ サーユイユイ
目差主ぬ くゆたらよ
ハーリヌチンダラ チンダラヨー二、ヒヤ 目差主や ばなんぱよ サーユイユイ
あたる親や くりゃおいすよ
ハーリヌチンダラ チンダラヨー三、ヒヤ んぱてぃから みささみよ サーユイユイ
べーるてぃから ゆくさみよ
ハーリヌチンダラ チンダラヨー
四、ヒヤ んぱてぃ者ぬ 見る目んよ サーユイユイ
べーるてぃ者ぬ 聞く耳よ
ハーリヌチンダラ チンダラヨー
(大意)
一、安里屋のクヤマは目差主に見染められました
二、目差主(の現地妻になること)はいやです
あたる親であればなっても構いません
三、そこまでいやだというならいいですよ
私にも考えがあります
四、あなた(クヤマ)がいやだと言ったことはしっかりと目に焼き付けました
しっかりと耳に入れました
一番はナレーション、二番はクヤマが、三番、四番は目差主が詠んでいるたとえです。
目差主は転勤で3年もすれば島を去ってしまいます。島を去る役人よりは、ずっと島にいる島の人がよいと、「あたる親(与人親、島の総代のようなもの)であれば乞われてもよい」とクヤマが二番で言っています。
三番はクヤマに袖にされた目差主のセリフです。
「んぱ」も「べーる」も「いや」という意味です。
四番では、たかだか農民の小娘が役人を突っぱねたことに腹を立てたいる様子を詠んでいます。
同じような内容を繰り返すことで、念押しして悔しがる役人の気持ちがよく表れていますね。
二十三番まではさすがに長いので割愛いたしますが、五番以降は目差主がクヤマ以上の美女を求めていく様子や、仲筋の美女イスケマとめでたく結ばれる様子が詠われています。
詩のなかでクヤマに触れているのは冒頭だけで、実は目差主が主人公の歌なのです。
娯楽の少ない時代、クヤマに袖にされたお役人を題材に面白可笑しく歌っていたのです。
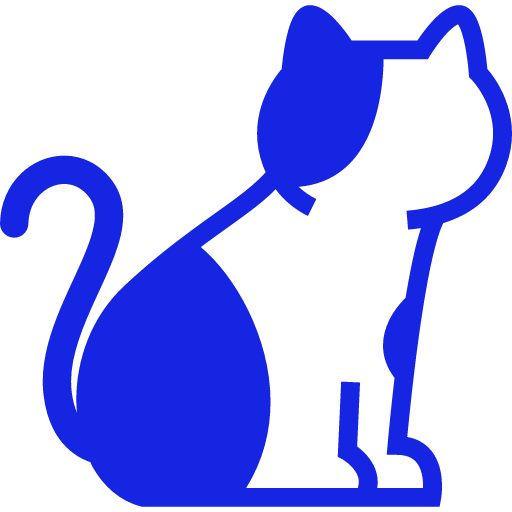 島風の記憶と希望
島風の記憶と希望 
